総務委員会行政視察 令和6年10月22日から24日まで
令和6年10月22日から24日まで、島根県出雲市、山口県下関市及び福岡県糸島市を視察しました。
NPO法人出雲スポーツ振興21の取組について【島根県出雲市(NPO法人出雲スポーツ振興21)】
取組の背景、目的

出雲市は、平成11年度を21世紀に向けたスポーツ振興元年と位置付け、出雲市総合スポーツ振興計画である「出雲スポーツ振興プラン21」を策定した。
この計画は、(1)人づくり、(2)環境づくり、(3)システムづくりの3本柱で策定し、プランを民間の立場で具現化する組織として、スポーツ関係者を中心に「NPO法人出雲スポーツ振興21」を立ち上げた。
NPO法人出雲スポーツ振興21は、出雲市総合スポレク祭を始めとした市民に直結したソフト事業や、市体育協会を始めとしたスポーツ振興団体の事務局業務、出雲ドームを始め9施設の管理・運営を引き継ぎ、平成12年4月より活動を開始した。
取組の内容
NPO法人出雲スポーツ振興21は、行政との役割分担をしっかりと意識して事業を行っている。市は、「まちの発展」につながる事業を担うこととなっており、主に、都市間連携、スポーツ施設整備、全国規模の大会等誘致、スポーツ団体への助成等を行っている。NPO法人は、「豊かな市民生活につながる市民のスポーツ振興」を担っており、スポーツ団体(体育協会・スポーツ少年団等)の事務局と団体間の横の連携支援、施設管理と利用者サービスのワンストップ化、総合型地域スポーツクラブの設立支援と運営等を行っている。行政とNPO法人が車の両輪となって、スポーツを活用したまちづくりに取り組んでいる。
法人の総務、財務の強化を図るため、会計の仕組みの変更及び人材育成の観点から人事制度の改革に取り組んだ。この取組により当法人は法人として自立し、発展していく団体となり、出雲市でのスポーツ振興に、継続して大きく関与している。
また、スポーツを通じた健康増進と社会参加の機会を提供しており、特に障がい者や高齢者に対する支援が拡充している。
課題
- 民間スポーツジムの参入により、公共スポーツ施設の利用が減少している。ただし、この点については、「民間ジムを使う、既にスポーツに取り組んでいる市民が増えることは良いこと」と捉え、NPO法人としては、日頃スポーツに取り組んで人へのアウトリーチが重要との認識だった。
- 体育館やプール等公共施設の老朽化による廃止に対し、施設の予防保全、長寿命化を図っていく必要がある。
- 東京の皇居のような、広くて明るい場所をつくるだけで、人は集い、歩いたり、走ったりすることを踏まえ、「皇居化計画(ラン・ウォーク)」を推進したい。そうした場所を構築する必要がある。
- スポーツツーリズムの推進を図っていく必要がある。
大府市への反映・所感
カリスマ理事長の手腕による経営改革によるところも大きいが、理事長の「市民にたくさんのスポーツをしてほしい」という思いがとても伝わってきた。
スポーツ振興の中心的な団体として、民間であるNPO法人が経営体制をしっかりと整え、自主自立運営を行っている点、定年制の創設・新卒採用も行い、継続的な体制づくりを行っている点、行政とNPO法人が担うことの仕分けがされている点は、本市において、スポーツ振興を行っていく上で参考になるものであると感じた。
NPO法人では、施設管理において施設利用料がNPO法人の収益とする仕組み、また、スポーツイベント時に弁当等の発注から会場設営の準備等までワンストップでサービスを仲介する「イベント支援事業」の仕組みにより、法人の収入源を増やし、黒字化を実現している。収益は施設管理やNPO法人の自主事業に充てており、例えば周辺市町に比べて指導料を高額に設定できることで、プロの指導者も多く確保でき、高品質なスポーツ教室が開催できているという。また、ワンストップサービスの仲介では、企画者側の手間の解消、NPO法人の収益増、そして地元企業への発注による地域経済の活性化にもつなげており、スポーツを通じていいサイクルをつくり上げていると感じた。こうした流れは本市でも参考になると思われ、この考え方から課題の洗い出しと解決法を探る必要があると感じた。
施設の管理・運営の在り方については、スポーツ施設の指定管理者を選定するだけではなく、スポーツ振興を担う組織の育成、運営体制の強化と新しいリーダーシップの確立が求められるのではないかと考える。
出雲市においては、利用施設が不足している場合、会議室等でも活動できるよう、施設の有効活用をしており、また、施設は予約制だが市民(団体)同士で調整できる関係性も大変参考になる。
市民がいつでもスポーツできる場を提供し、身体を動かし、元気でいられるよう、環境を整えなければならない。そして、スポーツに参加する人口を更に増やすための戦略的計画も必要ではないか。
下関市スポーツ施設の個別施設計画について【山口県下関市】
取組の背景、目的

人口減少や少子高齢化が進み、厳しい財政状況が続くことが見込まれる下関市では、合併等を経て、公共施設が他市より多い状況も踏まえ、今後の公共施設の維持管理及び更新等の在り方の方向付けのため、平成27年3月に「下関市公共施設マネジメント基本方針」を策定した。また、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、平成28年2月に「下関市公共施設等総合管理計画」を策定した。さらに、平成30年12月には、個別の施設の存廃、複合化や集約化、譲渡等の方向性を示すため、「公共施設の適正配置に関する方向性」を策定した。
これらの経過を踏まえ、下関市のスポーツ施設の現状を把握、整理した上で、具体的な対策や集約化等を計画的に実行することを目的として、令和2年6月に「スポーツ施設の個別計画」を策定した。
取組の内容
本計画での対策や集約化等は、下関市内40施設を対象とし、平成27年度から令和10年度までを計画期間として定めている。対象施設の建築年や延床面積などの基本情報を整理・集約化し、老朽化度や経済性などの現況情報と環境情報を整理・評価するとともに、施設所管部局と意見調整を行い、今後の方向性等(新総合体育館整備、集約施設の解体等)を施設ごとに取りまとめた。
新総合体育館の整備に当たり、既存施設の総量削減が求められる交付金を活用することを踏まえ、総合体育館から5km圏内において、その総面積の3割以上の集約が求められる中、統廃合に取り組んでいる。
また、下関市では、施設の総量削減・集約化と同時並行で、多様化するスポーツ施設ニーズに対応するため、令和6年度に「スポーツ施設整備補助金」を創設している。団体等が行うスポーツ施設等の新設又は改修する際、市民利用を前提に費用の一部を助成するもので、市が保有しない施設でも市民がスポーツできる環境整備を図っている。
今後の取組と課題等
令和7年度中に後期の計画(令和11年度から令和15年度)を含めた計画の見直しをしていく予定である。
課題としては、計画外の施設の改修対応が挙げられた。老朽化に伴う緊急的な対応や、市の政策に伴う計画外の改修対応、計画変更に伴う改修の取りやめなどが発生するため、計画どおりに改修を行っていくことが容易ではない点に苦労されている。
大府市への反映・所感
スポーツ施設の多面的な利用の拡充として、減少する人口に合わせた施設規模の見直しや、より多目的・柔軟な利用の仕方は、スポーツ施設が不足している本市でも再検討していかなければならない。
また、本市では施設の老朽化による維持管理が喫緊の課題となっているが、個別的な計画がない状況であり、スポーツ施設の現状を把握・整理した上で、個別施設ごとに具体的な対策や集約化等を計画的に実行するために策定した個別計画は、大いに参考になった。
予防保全にもつながるので、ぜひ本市でも取り組むべきである。
老朽化等に伴い、緊急的な修繕が発生し、下関市のように細かく計画を策定しても、計画どおりには容易に進まないであろうが、「健康都市おおぶ」だからこそ、スポーツ振興の要でもある「施設」に対しては、個別的かつ実効性が高い施設維持管理に関する計画が必要である。
下関市新総合体育館整備事業について【山口県下関市】
取組の背景、目的
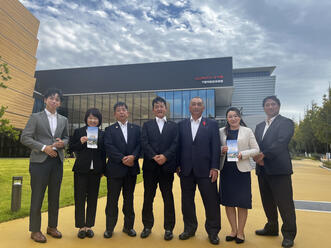
既存体育館である下関市体育館は築後57年を経過し、老朽化に加え、建築基準法に基づく新耐震基準を満たしておらず、利用者の安全性やバリアフリー性が懸念されていた。時代と共に変化する市民のニーズにも対応できなくなっている状況にあり、また、自然災害に備えた防災機能を有し、市の防災拠点となる施設の必要性も高まったことから、平成31年3月に「新総合体育館基本構想」、令和2年2月に「新総合体育館基本計画」を策定し、この計画に基づき実施している。
新総合体育館は、誰もがいつでも身近で気軽にスポーツを楽しむことのできる施設として、また、大規模大会や各種イベントが開催される、市の新たなスポーツ・レクリエーションを支える運動拠点として整備されている。
下関市新総合体育館整備事業は、BTO方式(※1)で行った。このBTO方式は、施設の設計・施工・維持管理・運営を一括して発注する方式であり、設計企業、建設企業、運営企業が互いにノウハウを活用することで、施設・運営品質の向上やコスト削減が期待できる。そして、建設資金の一部を民間事業者が調達するため、市の財政負担の平準化を図ることができ、また、金融機関によるモニタリング機能が働くことから、事業の安定的な継続も図ることができる。
新総合体育館では15年の維持管理・運営期間を想定しており、従来の指定管理者と比べて長期間の運営業務を行うこととなることから、民間の経営力やノウハウ、アイデアの発揮が期待される事業方式でもある。
下関市新総合体育館の建設においては、「見るスポーツ」の意識を持ちつつ、施設の集約化についても配慮して建設されており、スポーツ振興のきっかけとなる施設として期待されている。
※1:BTO方式
PFI手法の一つで“Build Transfer Operate”のこと。民間事業者が施設を建設(Build)した後、施設の所有権を市に移管(Transfer)したうえで、施設の運営(Operate)を行う形式。
大府市への反映・所感
下関市スポーツ推進計画の基本方針1の目標指標「市民のスポーツ実施率」は35.1%であり、大府市同様に低い数値となっていた。新施設を整備したことがスポーツ実施率の向上につながることを期待したい。
下関市新総合体育館の利用料は、指定管理者へ納めることになっており、利用料金制が採用されていた。本市でも、指定管理者制度の見直しの検討が必要ではないか。
またBTO事業により、メインアリーナの床材が民間の提案で傷つきにくい素材のものを取り入れるなど、民間のノウハウを十分に活用している様子がうかがえた。
下関市では、下関市体育館が築61年になる際に新総合体育館に移行していた。本市では、ナルキュウ体育センター(昭和54年開場)、メディアス体育館おおぶ(昭和60年開場)ともに築約40年を経過している。本市のスポーツ施設の10年後、20年後を見据え、「健康都市おおぶ」だからこそ、経過年数と維持管理をしっかりとシミュレーションする必要があり、建て替えも含めた既存のスポーツ施設の在り方を検討していかなければならない。
糸島市運動公園について【福岡県糸島市】
取組の背景、目的

糸島市では、平成24年2月に「総合運動公園の整備を求める請願」が各種スポーツ団体を始め、行政区長会、老人クラブ、子ども会育成会など、市内18団体から提出され、平成24年3月の定例会において、市議会が全会一致で請願を採択した。その後、市議会に「総合運動公園等調査特別委員会」が設置され、(1)「総合運動公園等の施設に防災機能を備えること」、(2)「市民が真に必要とし、利用しやすい施設を整備すること」、(3)「最小限の費用を持って、最大限の効果が得られるように努めること」の3項目が提言された。この提言を踏まえ、平成25年「運動公園等の整備に関する方針」、平成27年「糸島市運動公園等整備構想」、平成29年「糸島市運動公園等整備計画」を順次策定し、各段階において、様々な手法で市民の意見を把握しながら事業を進めた。
取組の内容
- 新設の総合運動公園を建設するに当たり、次の手法で市民の意見を集約し、多くの市民の意見を聴いて事業を進めた。
【方針策定段階】市内運動施設の利用者へのアンケート調査、普段運動に取り組んでいない市民モニター登録者への調査、市民満足度調査
【構想策定段階】市民アンケート調査、パブリックコメント
【事業実施段階】市民団体意見交換会(スポーツ協会、個別スポーツ団体、子育て支援団体、障がい者関連団体、防災士会) - 平成28年4月に「糸島市運動公園等整備検討委員会」を設置し、運動公園等の整備にかかる施設の規模、導入機能などの検討とあわせて、「糸島市公共施設等総合管理計画」を踏まえ、既存の13体育施設の統廃合について検討を行った。統廃合については、耐用年数経過を理由とした体育館2施設及び野球場1施設、稼働率の低下があった運動場2施設の計5施設について、廃止決定した。
- 施設の運営管理は、維持管理運営契約及び指定管理基本協定により、指定管理業務を行っている。令和5年度からオープンし、9カ月間における施設の利用率は順調に伸びているとのことだった。
- 予約方法は、市独自の「糸島市体育施設予約システム」によるインターネット予約または運動公園・多目的体育館窓口での予約である。支払い方法は、インターネット予約に限り、コンビニエンスストアでの決済を採用してる。
大府市への反映・所感
「これまでにない施設」が求められた糸島市では、「運動」機能に加えて「防災」機能をプラスした運動公園を整備した。災害時にスマホ等の充電ができる貴重品保管庫、マンホールトイレ、かまどベンチ、防災備蓄品の格納等、防災力の強化に力を注がれていた点は、本市でも大いに参考にしていただきたい。
糸島市が整備に至るまでに取り組んだ、多くの市民の意識調査等をしっかりと行って事業を進めた手法は大切であると思った。
運動公園は乳幼児から高齢者に至るまで、各年代で楽しめる公園として整備されており、一人の人が生涯にわたって、この運動公園を使って健康増進を図ることができるという、その発想はすばらしい。子どもから高齢者まで使いやすい工夫が施されており、広く市民の声を受け止めたことも感じられた。市の中心部にあるため、どの地域からもアクセスしやすく、また、障がい者スポーツの推進という点では、バリアフリーにも配慮が行き届いている。
予約には市独自のシステムを採用し、「いつでも・だれでも・どこでも」の考えから、施設が空いていればいつでも利用できる仕組みとしていた。これは、スポーツ振興につながるきっかけであり、本市も参考にすべき点であると感じた。
指定管理においては、利用料金制が採用されているが、15年という指定管理の期間で、経営の安定が想定される5年が経過した時点で、収益が想定の5パーセントを超えた場合は、その3割を市に還元してもらうという画期的な制度設計をしている。これは、事業者のモチベーションの維持にもつながり、ノウハウを駆使しながら、より良い維持管理が期待できると思われる。また、物価変動が指標の3パーセントを超えた場合、変更することができることが織り込済みとなっている点も画期的である。
これらの仕組みも参考にしながら、本市でも利用料金制を取り入れ、指定管理者が運営管理しやすくなるよう、検討してはどうかと考える。
また、空調費用に関しては、先に視察した出雲市、下関市と同様、糸島市でも施設利用料にならしている利用料体系であった。本市では、受益者負担の考えにより空調費用を利用者から別途徴収しているが、空調利用料が高いとの意見も多く聞かれる。物価変動や燃料費高騰、また昨今の猛暑にどのように対応するか、リスク分担等も含めた、マネジメント計画が必要であると感じた。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
